建設業許可
.png)
建設業許可申請を検討している方へ
こんなお悩みはございませんか?
建設業許可を取得したいが、申請手続きが複雑でよくわからない。
経営業務管理責任者や専任技術者の要件を満たせるか不安。
大きな金額の工事受注が決まり、急いで建設業許可を取得したい。
本業が忙しく、手続きを進める時間がない。
行政書士に依頼したいが、費用やサービス内容が気になる。
放置するとどうなる?
許可がないために大規模工事を受注できず、事業の成長が制限される。
書類不備や要件未達で申請が却下され、再申請に時間とコストがかかる。
格安な業務報酬の事務所に依頼したが、書類作成の一部が自己負担で手間が増える。
申請書作成のみのサポートで、行政庁との折衝を自分で行う必要があり負担が大きい。
解決策と当事務所のサービス
建設業許可申請は、書類の収集・作成・提出を含めた準備が非常に重要です。
当事務所では、
要件確認の徹底:お客様の状況に合わせた適切な許可取得方法を提案。
書類の収集・作成:行政庁が求める証明書類を精査し、確実に準備。
申請手続きの完全代行:行政庁とのやり取りや提出もすべて対応。
お客様の負担軽減:住民票や残高証明書の取得など、最低限のご協力のみでOK。
土日祝日対応可:お忙しい方も安心してご相談可能。
| 報酬(税込み) | 申請費用 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 新規申請(知事) | 110,000円 | 90,000円 | 200,000円 |
| 新規申請(大臣) | 165,000円 | 150,000円 | 315,000円 |
| 一般建設業更新(知事) | 55,000円 | 50,000円 | 105,000円 |
| 一般建設業更新(大臣) | 110,000円 | 50,000円 | 160,000円 |
| 特定建設業更新(知事) | 55,000円 | 50,000円 | 105,000円 |
| 特定建設業更新(大臣) | 110,000円 | 50,000円 | 160,000円 |
建設業の歴史と制度の流れ
建設業の制度は、古くは大工や棟梁の組織から始まり、現代の許可制度へと発展しました。
江戸時代:大工の棟梁が親方制度を通じて職人を指導。
明治時代:建設業の組織化が進み、施工管理の概念が登場。
昭和時代:戦後の復興とともに建設業許可制度が導入。
現在:社会のニーズに応じ、許可要件が厳格化。
職人の成長と「八・九・十」の流れ
建設業に携わる者がどのように成長し、一人前になり、組織を率いる立場になるのかを表すのが「八・九・十」という考え方です。
八人車(はちにんぐるま):見習いの職人。先輩や棟梁の指導のもと、基本技術を学ぶ。
九分の大工(きゅうぶのだいく):一人前の職人として認められ、仕事を任される。
十の棟梁(とうりょう):職人を束ね、工事全体を指揮するリーダーへ。
この成長の流れは、現代の建設業界においても通じるものがあります。許可を取得し、事業を拡大しながら、やがては自らが棟梁のように組織を率いる立場になることを目指す方も多いでしょう。
まずはお気軽にご相談ください!
✅ 無料相談受付中! お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
✅ 最短申請可能! お急ぎの方もスピーディーに対応します。
✅ 土日祝日も対応! お忙しい方も安心してご依頼いただけます。
電話 090-4745-8762
メール https://office-kamedanaoki.com/script/mailform/contact/
ライン https://line.me/ti/p/8w8xbIRLQC



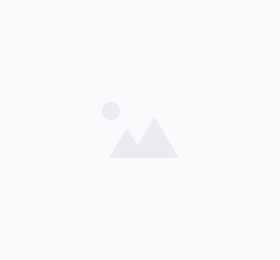
.png)

.png)

.png)
.png)
